ふう、やれやれ。
納品完了っと。
われながらいい記事が書けたわ。
晃くんが帰ってくるまでまだ間があるけど、はやめにご飯のしたくをしておこう。
きっとおなかぺこぺこにしてるだろうから。
わたしはあんなにおいしそうにご飯を食べる人を知らない。
わたしが作ったものを喜んで食べてくれるのもすごく嬉しいけれど、あの人は作り手の思いや苦心まできちんと味わってくれているんだと思う。
同じお料理でも、こまかな味付けの差や食材の切り方の違いなど、さらりと褒めてくれるのだけど、内心舌を巻いてしまうことがある。
なかなかそこまで気付くことはできないだろう。
彼がえらいのはお家での食事だけでなく、外食の時でも同じ態度でいることだ。
お料理を運んでくれた店員さんに必ず軽く会釈すること、食べ終わったお皿はテーブルの通路側に寄せておくこと、お会計のあとで「ごちそうさま」と、はにかんだように挨拶すること。
そして極めつけは、ただ食べるだけじゃなくて、自分でもどうにかして何かを作って、わたしを喜ばせようとしてくれること。
世の中には「グルメ」とか「食にうるさい」とか「舌が肥えた」とか、いろいろに例えられる偉い食いしん坊の人たちがいて、あがめられたりしている。
わたしも食通で知られたむかしの作家の作品が好きでよく読んだのだけど、その人が書いた食べ物のエッセイはどうしても好きになれなかった。
どれもものすごくおいしそうで、ノスタルジックで、思わずじゅるりとよだれが落ちそうな文章だ。
でも、それらはすべて、どっかりとあぐらを組んで運ばれてくるお膳を待ち受ける人の視点だった。
あれはいい、これはちょっとしたものだ、あの店は代が変わって味が落ちた、等々。
どれも間違っていないのかもしれないけれど、わたしは気に入らなかった。
ただ食べるだけの人よりも、拙くても真心こもった一皿を供せる人を、わたしは尊いと思う。
殴られて蹴られて、哀れなほど無様に負けたとしても、リングに上がって闘う人をただ見ているだけの人が笑う資格など、これっぽっちもないのと同じだ。
もちろん味を評するのにも相応の鍛錬がいるのだろうけど、やっぱりわたしは気に入らない。
じゃあ作ってみて。いますぐに。
意地悪くそう言ってやりたくなってしまう。
社会に出てから、男の人に食事をご馳走になる機会が急に増えた。
遅くなった仕事の帰りがけとか、食べ物の話題が出てちょっと盛り上がった瞬間とか、絶妙に断りづらいタイミングを捉えて声をかけてくる。
まだじゅうぶんに子どもだったわたしは、厚意と好意の違いにまったく不案内で、わざわざご飯を食べさせようとしてくれることにたいへん恐縮していた。
料理の流行にすごく敏感な人、ワインにすごく詳しい人、ドレスコードのあるようなお店にさらっと入っていける人。
いろんな人がいたけれど、誰もが食事そのものを楽しむというよりは、「こういうお店に案内できる自分」を誇るかのように振る舞っていた。
それはもちろん、血を吐くような思いで働いて得たお金で招待してくれたのだろうとは思う。
でも、お料理そのものの味は作った人の力だ。
それをあたかも、自分の力ででもあるかのように語ることが、わたしには言いようのない違和感となっていたのだ。
そういう人に限って、運ばれてくる料理に対してことさらに無関心なのも妙だった。
熱々を食べるべきものを冷めるまで放っておく、少し口を付けただけで大半を残す、食べながら延々とどこか外国の有名店の話をする、等々。
分からないのだろうか。
お魚のポワレの火加減に、料理人がどれだけ魂を削っているのか。
いちばんおいしいタイミングでお料理を出すよう、ギャルソンがどんなに気を配っているのか。
いまこのお店のお料理を心から楽しんでいる他のお客さんが、どんなに不快な思いでメニューの批評を耳にしているのか。
小娘がなにを知ったふうに、と思われても仕方ないかもしれない。
でも、男の人たちはたいてい、そんな小娘を相手に二軒目へと誘うことを忘れなかった。
隠れ家のような半地下のバーとか、夜景を一望できる高層のラウンジとか。
判で捺したような同じパターンに、ただの厚意で食事に連れて行ってくれるわけではないことをいやがうえにも思い知らされた。
申し訳ない気持ちはあるのだけど、それ以上付き合う義理などあるはずもない。
でも、ある時など二軒目のその後をきっぱり断ると態度が豹変し、「食い逃げかよ」と吐き捨てるように言われたことがある。
わたしはその場でお財布の中身を全部ぶちまけ、「ごちそうさまでした」と深々と頭を下げてバーを飛び出した。
ヒールを脱いで裸足でずんずん歩きながら、しゃくりあげて泣いた。
それ以来、食事のお誘いをいただいてもすべて断るようにした。
ご厚意だとわかっている場合でも、絶対に行かなかった。
わたしは自分のためだけに食卓をととのえて、長い間一人でご飯を食べた。
でも、あの人と初めて一緒にご飯を食べたのは、とても自然な流れだった。
お仕事が遅くなってふたりで会社を出て、もうおなかがぺこぺこで目の前にファミレスがあり、しかもぱらぱら雨が降ってきていた。
お仕事を通じて、その人の人となりになんとなく警戒心を解いていたのだけど、それでもある日のトラウマのせいでわたしはひどく緊張していた。
めいめい好きなものを注文して、最初に運ばれたお皿は忘れもしない、ピザだった。
すぐに切り分けようとしてくれたその人は、
「わあ、お皿があったかいですね」
と、嬉しそうに言ったのだ。
その瞬間、わたしの心を凍らせていたものが、じんわりと溶けだしていくのを感じた。
わたしが注文したパスタが先に運ばれてきたときも熱いうちに食べるよう強くすすめて、
「スパゲティの一秒は、ぼくらにとっての一年だそうです」
と、大まじめに言ったのも忘れられない。
わたしはほんとうに久しぶりに安心してたくさん食べ、それから何度も何度もその人と一緒にご飯を食べた。
ジャンクフードだろうが昨夜の残り物だろうが、その人と一緒だと何だっておいしかった。
いまだにわたしを「さん」付けで呼ぶのをやめようとしないその人が、もうすぐお家に帰ってくる。
今日は取材のためにお客さんのもとを訪ねると言っていたから、きっといつもより神経をすり減らせているだろう。
彼の大好きなおとうふと油揚げのお味噌汁、中くらいのハンバーグをふたつに半熟の目玉焼きをのせてあげよう。
サラダもたくさん食べてほしいから、疲れに負けず箸が進むようドレッシングにりんご酢を使おう。
どんな顔をして料理を頬張るか、ありありと想像できる。
わたしはらん、らん、らーん、と思いつきの歌を歌いながら、とっても楽しい気持ちでエプロンを身につけた。
 診断ツール
診断ツール
あなたが書くのに適した小説ジャンルは?小説執筆ジャンル適性診断


















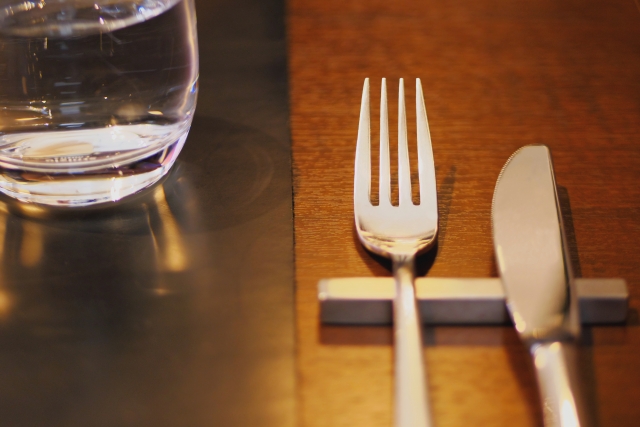
コメント